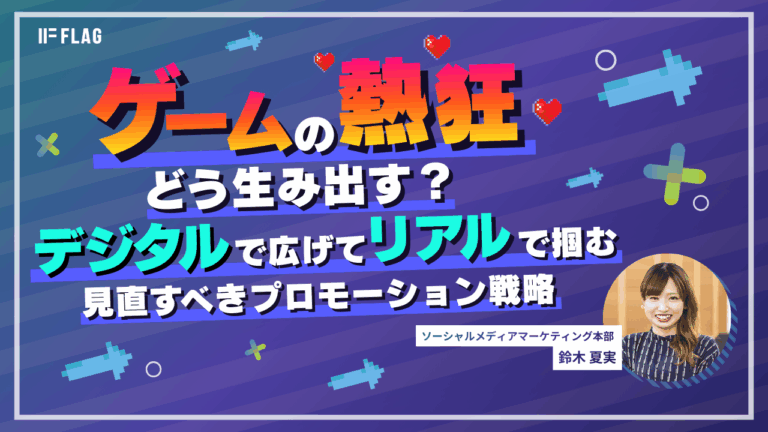- エンタメ業界
- 映画関連
【特別コラム:映画レビュアーインフルエンサー 茶一郎が執筆!】加速する「映画のショート動画化」と、いま「優しさ」がパンクになる理由は?映画業界の現状と今後を考察

概要
今回のコラムは特別版!映画作品のプロモーションを多数手がけるフラッグが、「映画レビュアー インフルエンサー」として活躍し、昨年は257本もの作品を鑑賞した茶一郎さんに執筆を依頼。
2025年のヒット作に見られる「映画のショート動画化」現象や、Netflixとハリウッドの逆転現象、そして分断が進む世界で映画が示した「優しさ」の価値。2026年の今だからこそ見えてくる映画業界の変化を、茶一郎さん独自の視点で解説していただきます。
第二弾はこちら:2,187人が選んだ「2026年新作映画」最も期待する作品ランキング
目次
- はじめに:優しさこそ“パンク”
- 加速する映画のショート動画化
- 「マンガ映画的」かつ「ショート動画的」なタイトル
- スマホスワイプさながらの映像体験
- 新しい映画は本当に必要なのか?
- 国内で相次いだ人気作の「リバイバル上映」
- 若年層からの支持も集め好調だった北米新作映画
- Netflixはハリウッドを破滅させるのか?それとも?
- Netflixによるワーナー・ブラザース買収
- 『ジェイ・ケリー』にみる、映画産業の重心移動
- 分極化が収束しないこの世界で、映画に何ができるのか?
- アリ・アスターが描く、アルゴリズムという名の「地獄」
- 『ワン・バトル・アフター・アナザー』が問う「真の愛情」
- さいごに
優しさこそ“パンク”だ——『スーパーマン』
私は何事も疑う性格。あなたは出会った人、全てを信じ、こう思っている“美しい”と……
—— それこそ真の“パンクロック”だ。
加速する映画のショート動画化
「マンガ映画的」かつ「ショート動画的」なタイトル
2025年の娯楽作品は、とにかく早かった!観客が直感的に感情移入できるキャラクターを配置し、ときに内面を言葉で整理させながら、俳優の息遣いすら置き去りにする速度で物語を運ぶ。さらに、単体で切り抜いてソーシャルの短尺動画としても成立するようなギャグシーンを大量投入し、気づけば映画が終わっている。
その象徴が、北米興収$424M(世界興収 約$958M)という大ヒットを記録した『マインクラフト/ザ・ムービー』だ。そして『ズートピア2』は世界興収$1.657Bに達し、アニメ作品として世界興行史上でも最上位級(歴代3位)に食い込む特大の成績を残した。
日本でも、実写邦画の歴代興収記録を更新した『国宝』は173億円超(興行通信社調べ)で旧記録を更新し、その後の累計では190億円規模に到達して日本における邦画実写の興収歴代一位となった。上映時間は3時間弱と長尺ながら、キャラクター配置は「血縁に恵まれない主人公」と「歌舞伎界のサラブレッドの血を継ぐ好敵手」の友情と競争という、少年漫画的に分かりやすい対立軸で組み上げられている。怒涛のスピードで主人公の一代記を描き切るその語り口は、ある種の「マンガ映画的」であり、同時に「ショート動画的」でもあった。
スマホスワイプさながらの映像体験
一方で、2025年は北米年間興収の上位がファミリー/アニメ系に寄り、ヒーロー映画は主役の座を独占できなかった。そのなかで『スーパーマン』は北米年間興収3位(約$354M)に食い込み、世界興収も約$617Mを積み上げた。しかも本作は、ジェームズ・ガンとピーター・サフラン体制で再始動したDCの新ユニバース(DCU)における長編映画としての実質的な第一手でもある。
ただし、観客が前提知識を共有していない新シリーズの1作目であるにもかかわらず、冒頭の短いテロップと数分の運びで世界観説明を終え、怒涛の速度で観客を新しいユニバースへ連れ込む。新しく登場するキャラクターの説明も、劇中のテレビ/ネットニュース映像に圧縮され、複数の画角・画質の映像が交互に差し込まれていく。
鑑賞中の感覚は、TikTokやYouTube Shortsで動画をスワイプしている感覚に近い。加えて本作は、超人的な能力を持った「メタヒューマン」の動きを追いかける素早いパンやカメラワークが多く、単純に映像の体感速度が速い。複数メディアを使った効率的な語りと合わさり、観客の思考が追いつく前に世界観へ吸い込む「ショート動画」時代の娯楽作品としての手触りが、強く残る一本だった。
新しい映画は本当に必要なのか?
国内で相次いだ人気作の「リバイバル上映」
2025年の日本興行では、リバイバル上映の存在感がいっそう強まった。『もののけ姫』4Kデジタルリマスターは週末ランキング上位に入り、上映形態もIMAX上映やDolby Cinemaへと拡張された。さらに『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年の限定上映は、公開初週末(2025年12月12日〜14日)で興収1億9802万4700円/動員8万5075人という数字を出している。
実際に映画館へ行くと、若い観客が多いことに驚かされる。かつて劇場で旧作を観た層だけでなく、旧作未体験の若い観客が「新しい映画」として旧作を求めている——少なくとも、そう見える場面が増えた。面白いかどうか分からない新作に賭けるより、評判が蓄積された旧作を選ぶのは自然な選択でもある。洋画文化の輪郭が薄くなりつつある今、「新しい映画」は本当に必要とされているのか?——そんな疑問が頭をよぎった一年でもあった。
若年層からの支持も集め好調だった北米新作映画
ただ、その疑問を跳ね返すように、北米では原作IPに依存しない新作映画が次々とヒットしたのも印象的だった。『罪人たち』は世界興収3.68億ドル、 『F1/エフワン』は世界興収6.32億ドル、 『WEAPONS/ウェポンズ』は世界興収2.69億ドル。 そして『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』は公開が年末寄りとはいえ、世界興収0.79億ドルまで伸ばしている。『サブスタンス』は世界興収0.77億ドル、 『ブルータリスト』は世界興収0.50億ドルと、 規模の大きさとは別の軸で熱量の高い支持を集めているタイプの作品だ。米レビューサイトLetterboxdなどを眺めても、特に若い映画ファンが強く支持していることが見えてくる。その中でも『サブスタンス』『罪人たち』『WEAPONS/ウェポンズ』は、いずれも広義にはホラーの領域に属する作品だ。
特にアメリカでスマッシュヒットした『WEAPONS/ウェポンズ』は、深夜2:17に、あるクラスの子どもたち17人が一斉に失踪した事件をめぐり、担任教師、保護者、警察官など複数視点で真相に迫るミステリー調のホラーだ。 ヒットの要因として断続的に視点が切り替わり、物語がリセットされ続ける構造そのものが、短尺動画の連続摂取にも似た感覚を呼び起こしたことも理由と考えられる。その一方で、運動(とくに「走る」こと)のバリエーションと速度のグラデーションで緊張を設計していく演出は高度で、デザイン性の高いホラー・ミステリーとして成立していた。
Netflixはハリウッドを破滅させるのか?それとも?
若年層からの支持も集め好調だった北米新作映画

昨年の映画関連ニュースで最も衝撃的だったのは、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの事業再編と、それに伴うNetflixによる買収合意だろう。もうハリウッドの新作を、映画館で観ることはできなくなるのか?そう身構えた映画ファンも少なくなかったはずだ。しかし皮肉なことに、著者が昨年もっとも「ハリウッド映画」を感じたのは、Netflixで配信された新作映画の数々だった。
『ジェイ・ケリー』にみる、映画産業の重心移動
とりわけノア・バームバック監督の最新作『ジェイ・ケリー』は、ある種の「ハリウッドの走馬灯」のような一本で、それをNetflixが製作・配信した事実自体が示唆的だ。
ジョージ・クルーニー演じるスター俳優ジェイ・ケリーが、イタリアでの授賞式へ向かう旅の途上で、俳優としてのキャリアと、これまで蔑ろにしてきた私生活の断絶に直面する。構造はベルイマン『野いちご』を、ハリウッド・スターに置き換えたかのようだ。クルーニーを筆頭に、献身的なマネージャー役のアダム・サンドラー、さらにローラ・ダン、ジム・ブロードベント、ビリー・クラダップ、パトリック・ウィルソンら、往年のハリウッド映画を支えてきた名優たちが演技アンサンブルを成立させる。そして終盤、授賞式の場面で仕掛けられる虚実ないまぜの演出は、「映画が映画であること」そのものへの執着と別れの感触を残す。
もし本作が「ハリウッド最後の映画」と呼ばれても強い違和感はない。繰り返しになるが、そうした映画が、今はNetflixでしか成立しにくいように見えること自体が、映画産業の大きな重心移動を物語っている。
分極化が収束しないこの世界で、映画に何ができるのか?
アリ・アスターが描く、アルゴリズムという名の「地獄」
数年前の娯楽映画では、トランプ政権以降に可視化された右派を一方的な悪として断罪する語りも目立った。だが2025年に強く印象に残ったのは、右か左かの単純な二項対立を避け、むしろ「共同体が同じ世界観を共有できなくなった現実」そのものを見つめる作品群だった。アリ・アスター監督の『エディントンへようこそ』は、その重要作の一つだ。
これまで「カルト村」や「家族」といった共同体の恐怖を描いてきた監督が本作で描いたのは、「ソーシャルメディアのアルゴリズム」による支配だ。 劇中、至る所に置かれたスマートフォンやパソコンの「画面」は、登場人物たちを閉じ込める「個々の世界」=「マルチバース」として機能する。同じユニバースを共有できない人々は、承認欲求のために思想すら浮動させながら、じわじわと地獄へ近づいていく。
『ワン・バトル・アフター・アナザー』が問う「真の愛情」
そして昨年、映画ファンの心を最も強く掴んだ一本として挙げたいのが、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ワン・バトル・アフター・アナザー』だ。本作もまた、過激化した右派と左派の闘争に挟まれる主人公を描く。
元革命家の主人公は、誘拐された娘を救うために奔走するが、危機的な状況にもかかわらず、左派の集団は合言葉を要求し、なかなか助けようとしない。主人公はついに「親の気持ちを考えろ」と憤る。ここで左派は、思想というより「感情を軽視するシステム」として戯画化される。一方で、主人公を追い詰める軍人も、ある保守集団への加入を試みながら、そこでは「真の愛情」を抑圧することが求められる。右も左も、いつの間にか人の感情を踏みつけるシステムに変貌している。 「今何時だ?」「今何時だ?」と合言葉を迫る集団に、主人公は「どうでもいい」(これが合言葉の返しだ)と一蹴する。子どもを救う親の前では、意味を失ったコードは無力だ。本作のキーアイテムである「トラスト・デバイス」は、デバイスを持つ者同士が対面すると、ひとつの旋律が立ち上がる。終盤に響くその音色は、いま目の前にいる人への愛情と思いやりの価値を、高らかに歌い上げる。愛情の前では、合言葉も、コードも、結局「どうでもいい」。
分断の時代に響く、「優しさ」という名のパンク

ここで思い出すのが、『スーパーマン』でクラーク・ケントが語った「“優しさ”こそがパンクロックだ」という言葉だ。人々が傷つけ合い、ソーシャルメディアに排外的な思考や差別的な言葉が溢れ返る時代において、他者への思いやりや、目の前の人を美しいと思うこと自体が、いつの間にか「パンク」な発想になってしまった。映画には、かつてのように分極化そのものを止める力はないのかもしれない。だが少なくとも、『スーパーマン』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』のように強い支持を受ける作品は、「止められない」と分かったうえで、それでもなお、目の前の人への感情、優しさ、思いやりこそが最も美しいのだと教えてくれる。
昨年末、ガザの情勢を受けたチャリティイベントに参加したとき、願い事として子どもが書いた「やさしさが増えますように」という言葉が、ずっと脳内で反響している。「優しさこそがパンク」になってしまった今の世界で、『スーパーマン』や『ワン・バトル・アフター・アナザー』が最後に残した手触りも、きっとそこへ帰着する——やさしさが増えますように。
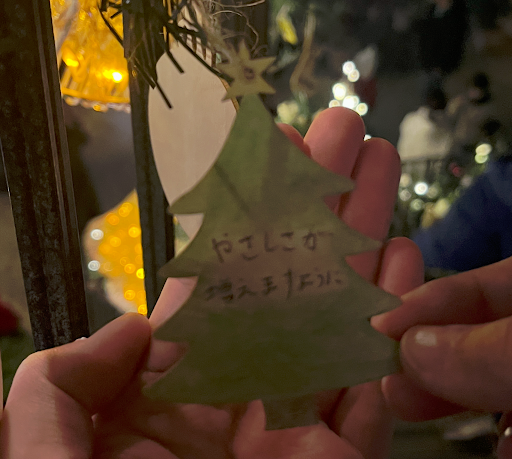
まったくムカつく“異星人”(Alien)だ!
—— そもそも、それが間違いだ。僕も“人間”(Human)だ。
人を愛し、何かに怯え、正解は分からなくても、まず一歩踏み出して、最良の選択を心がける。
ヘマばかりするけど、それが“人間”だ。僕の強さの源だ。
いつの日か世界にも分かってほしい。みんな強い人間だ。
『スーパーマン』
さいごに
以上、映画レビュアー 茶一郎さんによる特別コラムをお届けしました。第二弾もぜひあわせてご覧ください!

第二弾はこちら:2,187人が選んだ「2026年新作映画」最も期待する作品ランキング
フラッグは、映画・エンタメ業界の深い知見を元にクライアント・パートナーとともに、ワクワクなエンタメ体験を世界中に届けるマーケティングコミュニケーション会社です。
映画・エンタメに関するプロモーション案件のご相談はこちらから。

茶一郎
総フォロワー数82,000人超の映画レビュアーインフルエンサー。
情熱的な映画レビューと独自の視点で、多くの映画ファンに支持されている。
XやInstagramで最新の映画情報を発信し、FilmarksやYouTubeでも活動中。